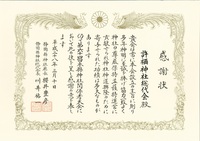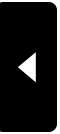2016年06月07日20:59
2016許禰神社だより 皐月(5月)
カテゴリー │許禰神社だより
桜の季節がすぎお茶もひと段落しいよいよ初夏を迎える季節となりました。
許禰神社も新体制になりましたが三倉地域の各神社も総代さんが交代しました。
そこで各祭事の際の作法等についての講習会を5月29日に行いました。


まずは社務所にて玉串の作り方からです。神社でよく見かける和紙で折った
ひらひらとした飾りを「紙垂(しで)」と言います。紙垂は雷光や稲妻を表し
落雷があると稲がよく育ち豊作になることや邪気を払うことに由来し玉串やしめ縄に使われます。和紙を折り切込を入れまた折って形を作り榊の枝に麻で結わえます。その後自分で作った玉串を持って拝殿にて玉串のあげ方を勉強しました。


また三方(さんぽう)と呼ばれる台に神饌物の載せ方をはじめ、神前にお供
えする時の作法などを学びました。細かい作法や所作がたくさんあり覚えるの
が大変ですが皆さん熱心に繰り返していました。
さて、6月19日(日)午前10時より許禰神社にて「夏越しの大祓」を執り行います。例年三倉地域の総代さんを招いて行っていますが一般の方の参列を歓迎しています。特に今回より和紙で型どった「人形(ひとがた)」をお祓いしみなさんにお配りし体の痛みのあるところや気をつけたいところをこすって清めるという人形祓いを行います。誰でもうけられますのでお誘い合わせの上お気軽に神社にお越し下さい。お待ちしております。
許禰神社も新体制になりましたが三倉地域の各神社も総代さんが交代しました。
そこで各祭事の際の作法等についての講習会を5月29日に行いました。


まずは社務所にて玉串の作り方からです。神社でよく見かける和紙で折った
ひらひらとした飾りを「紙垂(しで)」と言います。紙垂は雷光や稲妻を表し
落雷があると稲がよく育ち豊作になることや邪気を払うことに由来し玉串やしめ縄に使われます。和紙を折り切込を入れまた折って形を作り榊の枝に麻で結わえます。その後自分で作った玉串を持って拝殿にて玉串のあげ方を勉強しました。


また三方(さんぽう)と呼ばれる台に神饌物の載せ方をはじめ、神前にお供
えする時の作法などを学びました。細かい作法や所作がたくさんあり覚えるの
が大変ですが皆さん熱心に繰り返していました。
さて、6月19日(日)午前10時より許禰神社にて「夏越しの大祓」を執り行います。例年三倉地域の総代さんを招いて行っていますが一般の方の参列を歓迎しています。特に今回より和紙で型どった「人形(ひとがた)」をお祓いしみなさんにお配りし体の痛みのあるところや気をつけたいところをこすって清めるという人形祓いを行います。誰でもうけられますのでお誘い合わせの上お気軽に神社にお越し下さい。お待ちしております。
公式ブログにつき管理者が確認の上掲載させて頂きます